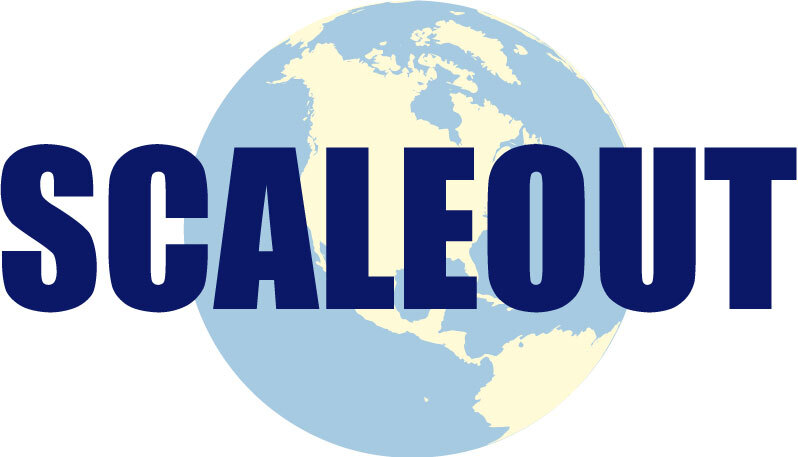STEAMで次世代の可能性を広げる – 篠山鳳鳴高校でのイノベーションとグローバルな協働の探究
2025-11-21
はじめに
私はエマニュエル・ニンシーマ(Emmanuel Ninsiima)です。JICA留学生であり、スケールアウト株式会社のインターンでもあります。このたび、兵庫県立篠山鳳鳴高等学校にて授業を行う機会をいただきました。

同校は現在、STEAM(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)教育に取り組んでおり、5つの分野を結びつけて、実社会の課題を解決する力を育む教育を進めています。
本取り組みは、JICA関西が実施する学校訪問プログラム「出前講座」の一環として行われました。このプログラムは、日本の学校の生徒さんたちが世界の専門家と交流し、イノベーションが社会にどのように貢献できるかを学ぶことで、国際的理解を育むことを目的としています。
スケールアウトでイノベーションを通じて国際的な協働を推進するインターンシップの一環として、このプログラムに参加できたことを嬉しく思います。
STEAM教育とは
変化のスピードがかつてないほど速い現代において、教育は単なる知識の習得にとどまらず、創造性・適応力・革新性を育む方向へ進化する必要があります。STEAM教育は、サイエンス・テクノロジー・エンジニアリング・アート・数学の5分野を統合し、論理的に考え、実社会の課題を解決し、学問を実践に結びつける新しい学びの形です。
つまり、技術的分野や創造的分野を組み合わせ、柔軟でバランスの取れた思考力を育てるのが STEAM です。「サイエンス」は好奇心や探究心を育み、「テクノロジー」はイノベーションのためのツールを提供します。「エンジニアリング」はデザインと課題解決を教え、「アート」は創造性と共感力を養い、「数学」は論理的思考と精密さを強化します。これらを総合的に学ぶことで、生徒さんたちは知識を社会的に意味のある課題へ応用する方法を学び、21世紀の社会をリードする力を身につけます。
第4次産業革命(4IR)
私たちはいま、第4次産業革命(4IR)の真っただ中にいます。デジタル・フィジカル・バイオロジーの各システムが融合する転換期であり、AI、ビッグデータ、ブロックチェーン、ロボティクス、IoT、クラウドコンピューティング、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、量子コンピューティング、自動運転、3D/4Dプリンティングなどの新たな技術が幅広い分野で社会を変革し、新たな機会を創出しています。
生徒さんたちにとって4IRの理解は、教室での学びを将来の仕事に結びつける架け橋のようになります。
ソサエティ5.0
今回の授業では、「ソサエティ5.0」についても紹介しました。これは、第4次産業革命の技術革新を基盤として、テクノロジーが人々の生活をより豊かにする「超スマート社会」の実現を目指すコンセプトです。内閣府によれば、ソサエティ5.0とは
「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」
と定義されています。
このビジョンは、日本が直面する少子高齢化、環境の持続可能性、経済格差といった課題に対し、イノベーション・包摂・共感を通じて解決の道を描くものです。
21世紀型スキルの育成
STEAMの学習活動や、第4次産業革命(4IR)およびソサエティ5.0の考えに触れることで、急速に変化する世界で活躍するために必要な21世紀型スキルについてもお話しました。これらのスキルは、従来の学問的知識を超えたものであり、論理的思考・協働・コミュニケーション・創造性が含まれます。こうした能力は、生徒さんたちが現代社会を自信・探究心・思いやりをもって歩む力を与えます。
また、STEAMの原則を現実の社会課題と結びつけるプロジェクトを企画・実践することもお勧めしました。その中では、プロジェクトマネジメントの主な段階──開始・計画・実行・モニタリング・評価・完了──を学びました。このプロセスを通して、生徒さんたちは知識・チームワーク・創造力を生かし、環境意識から社会イノベーションに至るまで、コミュニティの課題に取り組むことができます。
体験の共有と気づき
授業では、さらにデジタルトランスフォーメーション(DX)、サステナビリティ(持続可能性)、そしてイノベーションについての考えを共有しました。特に、ブロックチェーンやAIといったテクノロジーが、よい社会づくり(ソーシャルグッド)にどのように貢献できるかを強調しました。また、日本をはじめ世界の国々が、共感と協働を通じて、社会的・環境的課題をイノベーションによって解決する方法についても議論しました。
今回のような授業は、互いに学び合う場となります。生徒さんたちは、特にコミュニティ開発などに関し、テクノロジーを社会の前向きな変化に活かす創造的なアイデアを共有することができます。彼らの良心的な姿勢は、STEAM教育が単に技術的知識を養うだけでなく、国際的な視野や共に社会を支える責任感を育む教育であることを示していました。
まとめと感謝
生徒の皆さんはこの取り組みを通じて、自分自身や地域社会の課題を見つけ、アイデアを生み出し、効果的かつ持続可能な解決策を構築する力を学びました。
英語でのやり取りに少し苦労していた生徒さんもいましたが、彼らの真面目な姿勢は、グローバルな学びの精神を体現していました。
本プログラムの機会をくださったJICA関西 の皆さま、特に 津田かおり氏と 橋本亜矢氏に心より感謝申し上げます。また、温かく迎えてくださった笹山鳳鳴高校の先生方と学校関係者の皆さん にも深く御礼申し上げます。
このプログラムを通じて、若者たちが STEAM教育・第4次産業革命(4IR)・ソサエティ5.0 などを通じて、よりスマートで、持続可能で、思いやりのある社会を形づくっていく可能性を実感しています。
講義・執筆:エマニュエル・ニンシーマ (Emmanuel Ninsiima)
サポート:荻野浩司 (Hiroshi Oggy Ogino)、ダニエル・ルヨンガ (Daniel Ruyonga)
スケールアウト株式会社